
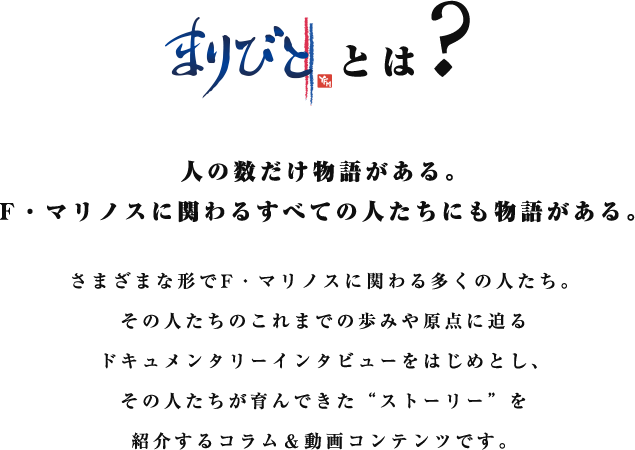



その生き様、オンリーワンである。
中町公祐の生き様。
文武両道で鳴らし、群馬の進学校から湘南ベルマーレに加入。
4年で契約非更新を受けると、在学していた慶応大学の体育会ソッカー部に入ってアマの世界からやり直した。
アビスパ福岡で再びJリーガーとなって頭角を現し、2012年より「あこがれにあこがれた」横浜F・マリノスの一員となった。
以降、F・マリノスを心から愛した背番号ハチのマチは欠かせない存在であり続けた。
「すべてはF・マリノスのために」身を捧げた7年間でもあった。
33歳になった彼は、ここで思いも寄らなかった行動に出る。
横浜を旅立ち、アフリカのザンビアに渡るという決断。
移籍が正式に決まらないまま、もっと言えば移籍に見通しが立たないまま、ザンビアに向かおうとしている。
視界不良のときほど、彼は明るく振る舞う。
アフリカ挑戦を報告した1月2日のSNSでも「なかなか誰も選択しないですよね(笑)」と文字で頭を掻いていた。
サヨナラに涙は要らない――。

実は、2018年夏ごろからアフリカ移籍を考えていた。
このシーズンで契約が切れるため、残り少なくなる現役キャリアの中で「自分にしかできないことは何か」を問い続けていた。
出した結論がアフリカでプレーすることだった。
中町とアフリカのかかわりは深い。
慶応大学時代の同級生が代表を務めるNPO法人を通じて、アフリカの恵まれない子供たちにサッカーボールを送る「PASS ON PROJECT in Africa」をスタートさせたのが2013年。
公式戦に勝利するごとにボールを届け、ロシアワールドカップの中断期間を使ってガーナに向かい、現地の子供たちとも交流した。
裸足で目を輝かせながらボールを追い掛ける姿は、中町の胸を打った。
中町のこだわりは、サッカーボールにF・マリノスのエンブレムを入れて、送り届けること。
アフリカの子供たちにF・マリノスを身近に感じてもらいたい、チームへのロイヤリティを形にしたい、サポーターにも何かを感じてもらいたい。
その思いを持って、送り届けたボールはアフリカ諸国80カ所、約500個にものぼった。
活動を次の段階に移すとき。彼は決断する。
アフリカの南部に位置するザンビアのサッカーは、2017年のU-20ワールドカップ韓国大会でベスト8まで進むなどメキメキと力をつけている。
国内のリーグも盛り上がりを見せているという。

「日本のサッカー界とアフリカのサッカーをつなげる、その一歩になれないかって思うようになってきたんです。僕がプレーすることで、日本人の目を、日本企業の目をアフリカに向けられないか。逆にアフリカの人の目を日本に向けることは出来ないかって。ボールだって、自分が直接、手渡せればいいんじゃないのかって。正直、ザンビアのリーグがどのようなレベルかも分からないけど、行ってみなきゃ分からないですから(笑)。
クラブには感謝しています。今回、複数年の延長のオファーをいただきました。33歳の僕に、それも試合にあまり出ていないのに、あり得ないこと。ただチームを編成する上で時間的なリミットがあるため、移籍の見通しが立たない中でF・マリノスを離れる決断を下しました。まあ、勝手にですけど、F・マリノスを背負ってアフリカに行くという思いです。移籍が実現せず、フリーランスになる可能性も十分にありますけど(笑)」
センチメンタルは苦手。
明るく笑って、困難を往く。マチには、それがよく似合う。
「やっぱり大学での経験が大きかったんじゃないかなって思う」
中町を語るうえで、慶応ソッカー部時代は外せない。
高崎高から勉学で慶応大学に進み、ベルマーレから契約非更新となったために大学の部に入ったという流れ。
「プロで自分の何が足りなかったのか分からないまま、アマチュアに戻ったわけです。部では僕のほうが年上になるし、周りの学生だってやりにくそうにしているのは肌で伝わってきましたよ。だから水汲み、ラインズマン、ビデオ係……何でも率先してやるようにしました。周りとの信頼関係を築いていくことを優先したかったので」
あるとき、試合用の短パンを忘れてしまったことがあった。
チームメイトに借りようとしたが、「マチそれはダメだよ」と冷たい視線を浴びることになる。
信頼を得ようとしてやってきたのに、逆に信頼を損なうことになった。
「プロなら着るものも全部用意されている。当然ですけど、アマは全部、自分たちで用意しなきゃいけない。短パンを忘れて、部員に『本日、短パンを忘れてしまいました。ひいては18時に合宿所に集まっていただき~』ってメールを送り、ミーティングを2時間、4セットやりました。プロなら実力社会で、力関係が働くじゃないですか。でも大学は、たとえばCチームの選手がトップチームの選手に『お前、その姿勢じゃダメ』と言える世界。
一度失った信頼を取り戻すことがどれほど大変なのかを学ばせてもらったのです」
チームメイトの信頼を勝ち取り、組織として戦う喜びを感じた。
慶応ソッカー部を関東大学サッカーリーグ2部から1部に引き上げるなど、その成功体験を得ることができた。
F・マリノスでも何より大事にしていたのは、チームメイトとの信頼関係だった。
Jリーグ開幕時からの「マリノス派」。
少年時代にエンブレムのついたキャップをかぶり、グッズを身につけた。
2012年、26歳になってようやくあこがれのクラブにたどり着いた。
しかし、みなとみらいのクラブハウスで感じたのはちょっとした疎外感。
アットホームというよりは、一人ひとりが独立した集団のように思えた。
「周りから期待されて入ったわけじゃないって、よく分かった」
視界不良のときほど燃えるタイプ。チームメイトと積極的に交流し、プレーでも仲間のためにパスを出し、体をぶつけ、走った。
一人よがりのプレーを戒め、周りに気持ちよく動いてもらうための潤滑油になることを心掛けた。

「まずは自分が味方を信頼し、逆にコイツなら信頼できると思ってくれたら、頑張ってパスを受け取ってくれようとする。ちょっとパスがずれたって、助けてくれる。もちろん自分も(チームメイトを)助けたいって思う。そういう組織が強いんだって、ずっと思ってきましたから。俺は目立たなくていい。強い信頼関係があれば、瀬戸際に立ったときにみんなで助け合うことができる」
個と個をつなぐ、リンクマン。
一つ実を結んだのが移籍2年目の2013年シーズン。
リーグ優勝に王手を掛けながら取り逃がしたものの、「円陣を組んだだけで、このチームは負けないと思えた。周りのことも自分の責任だとみんなが思っていた」。
富澤清太郎とのコンビでチームを支えた。
しかし信頼関係を築くには、甘い顔をするだけじゃ本物にならない。厳しいことも言った。
移籍を希望する若手に対し、「ここで成功することから逃げたら、ほかのクラブに行っても通用しないぞ」と突き放したこともある。
信頼関係はチームメイトのみならず、サポーターや社員とも。
中町は誰よりもファンサービスを大切にした。
誰が言ったか「ファンサ日本代表」。
雨が降ろうが風が吹こうが、念入りに丁寧に対応することを忘れなかった。
この背景にはアビスパ福岡で過ごした2年間が大きかったという。
「サポーターとの距離が近くて毎日、練習が終わって1時間以上、ファンサービスをしたこともありました。でもサポーターの期待を活力に変える喜びが僕にはあった。F・マリノスでは実施の回数が限られているので、きちんと手厚くやりたかった」
選手会長に就任すると、ファン、サポーターのことを考えていろんな企画を打ち出していく。
今や定着したユニフォーム付きチケットも「アビスパのときに、福岡ソフトバンクホークスが取り入れて、凄くいいなと思った」中町の発案。
選手とファン、サポーターが一体となって盛り上がる音楽イベント「マリノスナイト」もそうだ。
社員とも意見をぶつけ合って、企画を実現させてきた。
選手もファン、サポーターもスタッフも、社員も。
「エンブレムにロイヤリティを持った選手の集団にしたい」という思いで、ピッチ内外で奔走した。

最高に幸せで、最高の宝物。
中町は7年間のF・マリノスを振り返って、そう表現した。言葉を一度噛みしめてから、再び語り始めていく。
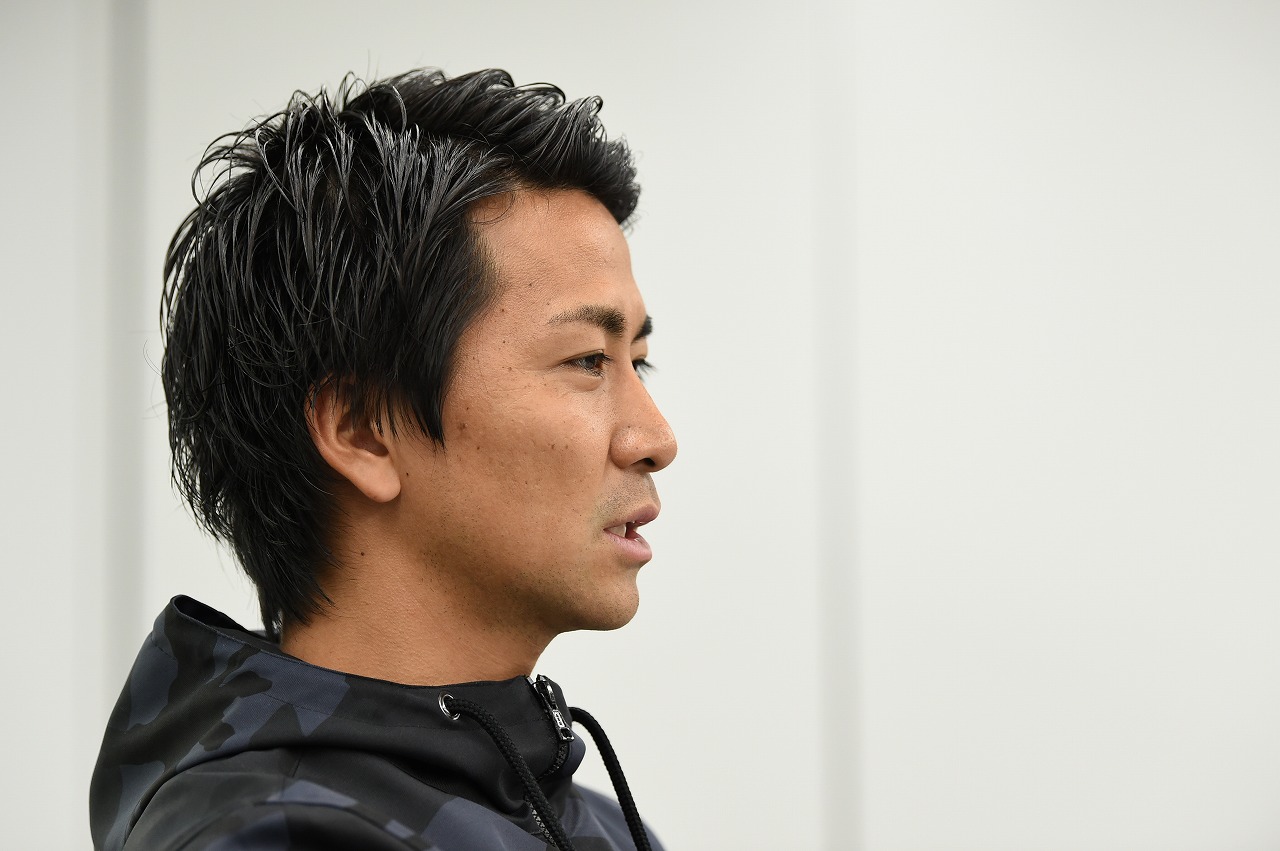
「俺自身が活躍して自分の価値を上げていくことよりも、みんな一緒になって組織的に改革していくことが何よりも楽しかった。
会社の人も企画を歓迎してくれました。単に盛り上がればいいとか人を集めたいとかそういうことじゃなくて、すべての大義はF・マリノスのため。心の底からそう言えます。
2年前にJ1のあるクラブからオファーをいただきましたけど、違うエンブレムをつけるイメージがわかなかった。
F・マリノス以外の日本のクラブで、ここまでのモチベーションではやれないと思いました。
僕は功労者でも何でもないですよ。
でも愛情を目いっぱい注いだし、逆にクラブもリスペクトしてくれて愛情を感じました。本当に最高でした。
ザンビアのことがあったので今回のマリノスナイトに参加できなかったのはちょっと残念でしたけど」
自分を代表とするNPOを設立する。代理人を置かない彼は単身、ザンビアに渡って移籍予定のクラブと最終交渉に入る。
中町は2015年12月、長男・彪護(ひゅうご)くんを亡くした。心拍が確認できない状態で誕生し、生まれて43時間で息を引き取った。F・マリノスでは「ひゅうごシート」を設置し、神奈川県立こども医療センターの協力のもとNICU(新生児特定集中治療室)出身者やその家族たちを招待してきた。アフリカ諸国の乳幼児の死亡率を知って胸を痛めたことも、アフリカに関心を抱くきっかけになった。

天国の愛息にも背中を押されて、いざアフリカへ。
中町公祐は、真面目な顔をつくってから言った。
「俺は一人でも多くの人の期待を背負ってピッチに立ちたい人間なんです。人の幸せが、自分の幸せになる。それが大きくなっていけばいくほどハッピーになるし、自分の人生が豊かになっていく。だからアフリカでも、サッカーをコミュニケーションツールにしていろんな期待を背負い、周りの人も自分もハッピーになっていければいいなって思っています」
横浜のマチを盛り上げ、人をつなげ、新たなカチをF・マリノスにもたらした。
横浜からアフリカへ。
新たな旅に出るマチに、サチあれ――。

二宮寿朗Toshio Ninomiya
1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載
