
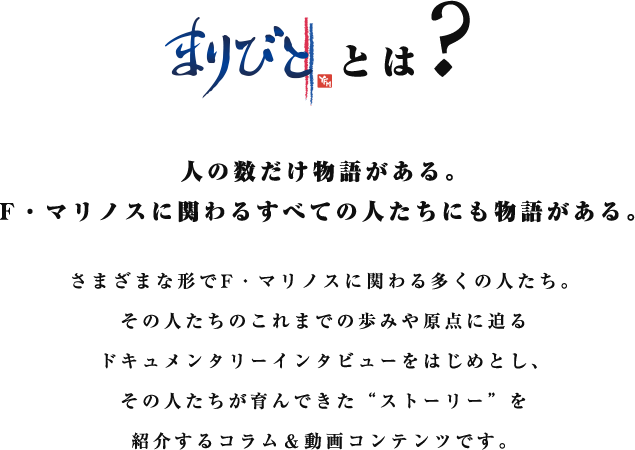



誰が呼んだか、ハマの番長。
2年前に現役を引退した横浜DeNAベイスターズの三浦大輔さんはリーゼントのヘアスタイルからこのニックネームが生まれたが、栗原勇蔵の背景はまた違う。武闘派エピソード満載ゆえに自然発生した感がある。
ユースから昇格して横浜F・マリノス一筋。堅守を受け継ぐ者として、ストライカーとのタイマン勝負を制してきた。
今年、プロ17年目、34歳になった。血気盛んだった20代前後のころと比べれば随分と落ち着いているようにも思えるが、心の奥底の〝やんちゃマインド〟は健在だ。
若気の至りが「ユウゾウ伝説」となり、尾ひれがついている武闘派エピソードもある。クラブ愛の至りから、残留を決断した熱血派エピソードもある。
現役最終章に向かう彼をしっかりと味わうためにも、本人公認「まとめ」を企画しました。どうぞ笑ってください、どうぞ驚いてください。どうぞ栗原勇蔵の今の思いを知ってください。

――これほどエピソードの多い選手も珍しい。一つひとつ真偽を確かめていきましょうか。
まずプロ2年目の2003年、岡田武史監督が就任してあるとき「お前、ケンカ負けたことないだろ?」と声を掛けられたというのは本当?
番長「本当っすね。東戸塚のグラウンドで岡田さんが近づいてきて『悪いツラしてんなあ、目ツキ悪いなあ』って。まあ確かに、高校卒業してまだガキだったし、何て言うんすか、目をそらしたら負けという感覚をサッカーのほうにも持ち込んでいて、その勢いだったから」

――岡田さんにもガンを飛ばしたとか?
番長「あるわけないでしょ(笑)。だけど岡田さんはジェスチャー付きで言ってくれたよ。『俺も昔はこれ(リーゼント)とこれ(ボンタン)だったんだ』と。俺のことを分かってくれている感じがあったね」
――腕っぷしには相当自信があったんでしょ
番長「まあ、そうっすね」
――中学時代に背筋テストで200㎏以上。何すか、この凄い数字は?
番長「先生に疑われて、5回ぐらいやらされて背筋痛めた苦い記憶がありますね。背筋力は母ちゃんが強くて、同じ中学の最高記録を持っていた。男が俺」
――その太い腕から「マグワイア」(メジャーリーグのホームランバッター)と呼ばれていたというのも本当?
番長「本当。中3にしては太かったというだけだけど。サミー・ソーサとホームラン争いして知っていたし、悪い気はしなかった」
――ゲームセンターのパンチングマシンでこれまた凄い数字を出して、ボクシングジムの人に勧誘された話は、僕も2003年に聞きました。
番長「誘われたというか、声を掛けられた程度だけど。俺の体、大きかったし、日本で重い階級のボクサーって昔は凄く多かったってわけじゃないでしょ。だから本気で誘った感じではなかったけどね。ただ、出した数字にビックリされたことは覚えている。(都筑区の)花形ボクシングジムの人って言ってたね」
――武闘派の顔は味方からも恐れられていきます。
番長「この場を借りて、懺悔したいことが……」
――どうぞ、どうぞ。
番長「2003年のときだったかな。練習前に1つ年上の金子勇樹とふざけて、プロレスやっていたんですよ。アルゼンチンバックブリーカー(かつきあげて背中を痛めつけるプロレス技)の変形でちょっと力を入れすぎたら、金子クンが気絶してしまって……」
――先輩にアルゼンチンバックブリーカーって。
番長「金子クン、気を取り戻したら超テンション、低くて。いや、申し訳なかった(苦笑)」
――試合中でも味方がゴールを決めると、あなたの手荒い祝福が待っていました。伝説になっているのが、2004年5月のACLグループリーグ、アウェーの城南一和戦。ゴールを決めた河合竜二選手に思い切り抱き着いたら、ラリアット(相手の首に腕を叩き込むプロレス技)を決めてしまいました。
番長「うーん、あれは先にホームで負けていたから、竜ちゃんのゴールがメチャクチャうれしかったわけ。竜ちゃんもうれしいから、お互いに浮いて飛びついたら、俺の手がいい角度で先に首に入ってしまった。うれしすぎて結果的にああなっただけ」
――2003年のワールドユースでは、クラブで同期の坂田大輔がゴールを決めた後、馬乗りになっての祝福でした。
番長「サカティがゴールを決めてもちょっとスカしていたんで、もうちょっと喜べやという意味をこめて」
――なるほど、嬉しさ余っての手荒さだ、と。どの祝福が思い出深いですか?
番長「山ちゃん(山瀬幸宏)が大分戦で、ロングシュートをズドンと決めたことがあって(2008年5月、ヤマザキナビスコカップ)。いつもクールで、物静か。その山ちゃんが興奮しすぎて俺のほうに寄ってきたんで、もうもみくちゃに。俺の手荒い祝福以上に、あんなにうれしそうな山ちゃんの表情を見られたことがうれしかった。今でも忘れられないシーンです」

――あと、いろんなイタズラもやってきましたよね。プッと笑えるというよりも、こちらもかなり手荒い。
番長「ん? サロメチール(筋肉疲労に効く薬)をパンツに塗ったこと?」
――手荒いというよりひどい。よくバレなかったですね。
番長「トレーニングパンツってインナーがついていて、色が白。前日に塗り込んでおくと、サロメチールも白だから乾いて同化する。翌日、練習して汗をかくとね、下半身にひっついて痛くなる。ミカさん(三上和良)とか金子勇樹は飛び上がって〝誰がやったんだ!〟って怒るんだけど、名乗り出ない。遠くで見て、笑ってましたよ。フフ、フフフフフ」
――そのアイデアは誰から?
番長「いや、もちろん俺も誰かにやられていて、それも名乗り出ない。ミカさん、金子クンには申し訳ないが、やってみたら面白かった。ちょっと大げさに言うと、当時は真面目が強い人1割、真面目が弱い人9割。だからこんなイタズラ日常茶飯事っす」
――うまく言えば、それもコミュニケーションというか。
番長「そうそう、コミュニケーション。先輩とのコミュニケーションです」
――ピッチ上でも武闘派は発揮されます。2003年にはワールドユースの壮行試合で乱闘騒動もありました。F・マリノスでも「やられたらやり返す」くらいの迫力が常にあった。忘れられないのがレッジーナとの親善試合(2004年8月)。セットプレーで相手選手のエルボーを食らい、鼻骨を骨折しました。鼻から血を流しながらその選手を追い掛けていました。

番長「あんな悪質なファウルやったらダメでしょ。俺たちサッカー選手なんだから。コーナーキックのときにパンチ食らっていて〝オイッ〟て服を引っ張った勢いで、鼻にバコーンって入って。前半からレフェリーに文句言ったり、ボールを思い切り蹴り上げたり、イライラしているのは分かっていた。こっちは鼻折られたわけだし、カチンときた。あのラフプレーは許せない。翌日、空港まで行って胸ぐらでもつかまないと気が済まなかった。でもあのとき、ちょっとしたオチがあって……」
――オチ?
番長「怒りが収まらないからベンチに戻って、思い切り蹴り上げたわけ。そうしたらベンチの間に足が挟まって、抜けなくなった。ダッサー、俺、と思ったね」
――日本代表のデビュー戦となった親善試合トリニダード・トバゴ戦ではいきなりの接触プレーで、相手のほうがタンカで運ばれていきました。
番長「ツボさん(坪井慶介)が足つって、出場することになった。サッカー人生で初めて武者震いした。相手はすごくゴツくて、絶対に負けねえって気持ちでいったら、削ったみたいになった。30分ぐらいの出場だったけど、アドレナリンマックスの状態だったね」
――武闘派で鳴らしていますが、あくまでクリーンファイト上でのこと。
番長「25、26歳ぐらいまでは相手に〝なめられたくない〟と思ってやってはいたけど、年齢を重ねるにつれて、変な言い方だけど、相手だってサッカー仲間っちゃ仲間。別に敵じゃないわけだから。自分の抑えも利いてくるし、余計なことをやったことってないから」
――F・マリノス一筋17年目。アクの強い先輩たちもいっぱいいました。選手のキャラクターも昔と今では全然違う?
番長「昔は人間味あふれる感じの人が多かった。前日遅くまで遊んでいても、練習が始まったら全然違う。かっこいいなって思いましたよ。でも今の時代はプロ意識がみんな高いし、サッカーだけを考えるなら今のほうがいい時代なのかもしれない。俺はどちらも知っているから、どちらの良さも分かってるつもり」

――近年はケガが相次ぎ、出場機会が少なくなってきています。それでもこのクラブに居続ける決断をした背景にはどのような思いがあった、と?
番長「一番はこのクラブから離れたくなかった。横浜という町からも。マリノスからオファーがあっただけでもうれしかった。ただ一方で俺のことを思って、いい条件でオファーをくれたクラブもあった。これも嬉しかった。だけど自分なりに考えてみて、ここに居続けるヤツがいてもいいんじゃないかって思った。ここで終われるなら、それが一番いい」
――現状、試合にはなかなか出られていない。
番長「そう、そこは葛藤しているところ。過信はしないけど、自信がないとやっていけない世界。できないと思ったら、そこで引退だろうね。でも同じ年齢のヤツと比べても、俺はまだまだやれるって思っている。ウチのセンターバックはみんな頑丈だし、なかなかチャンスは回ってこないけど、俺は試合に出ていない割には(実力が)落ちていないって感じている。1試合だけってなると難しいけど、1、2戦こなして試合に慣れれば絶対にやれる自信が俺にはある。やれるというか、(相手に)やられる気がしない」
――やり残したことがありそうですね。
番長「ここ2、3年あまり試合に出ていなくても、このチームにいるわけだからこのまま終わりたくはない。出ていないときが無駄じゃなかったんだと思いたい。試合に出ていない今の弱い立場の俺を、応援してくれる人はたくさんいる。すごく心に響くというか、その人たちのためにもとは思う。サッカーはメンタルのスポーツ。数字では表せない存在感ってあると思うんですよ。アイツがいるだけで、何か嫌だなっていう存在感。今までやってきて、やっぱりそこは出せると思うから」
――これからの栗原勇蔵、どうありたい?
番長「何だろうな、難しいな。でも……」
――でも?
番長「言葉にするなら、もうひと花咲かせたい。それだけだね」
日産フィールド小机は初夏のように、太陽が強く自己主張している。
武闘派のイタズラ好きはインタビューの後、大きく深呼吸して雲ひとつない空に視線を送ってから、歩を進めていく。
もうひと花咲かせたい。
栗原勇蔵の「まとめ」は未完成だ。とびっきりのエピソードは、きっとこの先にある。

二宮寿朗Toshio Ninomiya
1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載
